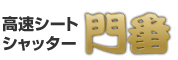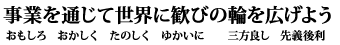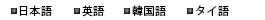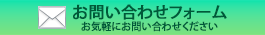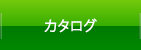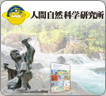お客様紹介
| 社 名 | 奥出雲仁多米株式会社(Webサイト) |
| 事業所 | 島根県仁多郡奥出雲町高尾1787-22(仁多郡カントリーエレベーター内) |
| 代表者 | 代表取締役 勝田 康則 |
| 創 立 | 1998(平成10)年4月27日 |
| 従業員数 | 12名 |
| 事業内容 | 米穀小売業と、付帯する一切の業務 |
島根、奥出雲町から全国に広がる「仁多米」ブランド。
夏場に昼夜の寒暖差があり、ミネラルが豊富な地下水がある同地方産の米は、かつては知る人ぞ知る"うまいコメ"だった。
そのブランド化作戦が本格的に始動したのは、1998年のこと。
今摺り(米の鮮度を保つため、出荷直前の精米)、直販を掛け声に、貯蔵能力3000tのカントリーエレベーターをもつ販売会社「奥出雲仁多米株式会社」が発足してからのこと。
わずか10数年で全国ブランドに育てた同社は、品質確保と工場内の清潔な環境を維持するために、門番を使っていただいている。

米の登熟期である夏場の寒暖差が、仁多米の旨さを支える
実際にご利用いただいて
夏場の精米ルームの室温は、結露せず、品質を保つ最適な温度として27〜28℃を維持している。同社に門番GF10型を導入頂いたのは2010年3月。
それまではルームと出荷場の間仕切りが、ビニールカーテンだった。
当時から精米を担当されている山田薫さんはいう。
「門番を設置してみると、冷房の効きがいいんですね。精米の時の粉塵が外に漏れるのは、激減しました。センサーで開閉するので作業に負担がない」
導入頂いたのは、こうした具体的な効果もさることながら、「仁多米」ブランドを維持するためのイメージアップも大きいとのこと。
仁多米の売り上げは、カタログ等による通信販売が今では40%を占める。
価格を維持しながら通販を広げるには、食品の隅々まで知る商社担当者が「美味い、安全な」米を安定的に出荷できる工場だと、太鼓判を押す設備でなければならない。
「カタログギフトを扱う商社が来た時に、ビニールカーテンを見て指摘があった。
グレードの高い販売のために門番は必要と思いました。
購買層に伝えるためには、米も加工食品ですから、きちっとした精米ルームがなければならない。品質確保のためのアピールとしての効果も大きいです」(業務課長、内田康也さん)
始めは年間750tの出荷からスタートした仁多米は、年々増加を続け、今では年間1100tに。
全国の一流百貨店のカタログギフトで使われるなど、定着してきた。
2012年2月にはブランド化10周年記念の振興大会が町内で開かれている。
「世の中が変わり、『米もいいものを食べよう』という価値観がでてきました。
仁多米は、そういう意識の変化に合わせて、販社をつくることから始まったんです」(常務、三澤又三郎さん)
「精米過程で年間 60tの米ぬかが出ますが、シイタケをつくった廃ホダ木、牛糞とともに、堆肥センターで完熟たい肥になって、土に戻ります。これは我が町独自の環境循環型農法です。全国にない特色ではないでしょうか」(内田さん)
仁多牛、シイタケは、仁多米とともにブランドとして全国に知られる存在。
近年はお米の一部が銘酒仁多米の米焼酎にもなっている。
町の自慢を"有機的に"繋げて、循環させながら全国出荷を続ける奥出雲町。
門番はそれを支える、一翼を担わせていただいている。

それまではルームと出荷場の間仕切りが、ビニールカーテンだった。
当時から精米を担当されている山田薫さんはいう。
「門番を設置してみると、冷房の効きがいいんですね。精米の時の粉塵が外に漏れるのは、激減しました。センサーで開閉するので作業に負担がない」
導入頂いたのは、こうした具体的な効果もさることながら、「仁多米」ブランドを維持するためのイメージアップも大きいとのこと。
仁多米の売り上げは、カタログ等による通信販売が今では40%を占める。
価格を維持しながら通販を広げるには、食品の隅々まで知る商社担当者が「美味い、安全な」米を安定的に出荷できる工場だと、太鼓判を押す設備でなければならない。
「カタログギフトを扱う商社が来た時に、ビニールカーテンを見て指摘があった。
グレードの高い販売のために門番は必要と思いました。
購買層に伝えるためには、米も加工食品ですから、きちっとした精米ルームがなければならない。品質確保のためのアピールとしての効果も大きいです」(業務課長、内田康也さん)
始めは年間750tの出荷からスタートした仁多米は、年々増加を続け、今では年間1100tに。
全国の一流百貨店のカタログギフトで使われるなど、定着してきた。
2012年2月にはブランド化10周年記念の振興大会が町内で開かれている。
「世の中が変わり、『米もいいものを食べよう』という価値観がでてきました。
仁多米は、そういう意識の変化に合わせて、販社をつくることから始まったんです」(常務、三澤又三郎さん)
「精米過程で年間 60tの米ぬかが出ますが、シイタケをつくった廃ホダ木、牛糞とともに、堆肥センターで完熟たい肥になって、土に戻ります。これは我が町独自の環境循環型農法です。全国にない特色ではないでしょうか」(内田さん)
仁多牛、シイタケは、仁多米とともにブランドとして全国に知られる存在。
近年はお米の一部が銘酒仁多米の米焼酎にもなっている。
町の自慢を"有機的に"繋げて、循環させながら全国出荷を続ける奥出雲町。
門番はそれを支える、一翼を担わせていただいている。

出荷直前の精米が、仁多米の鮮度を保つ